
ネット通販の普及により、家電も自宅で手軽に購入できる時代になりました。
しかし、「ネットで買わない方がいい家電」という言葉を耳にして、本当にオンラインで買って大丈夫なのか不安に感じていませんか?
ネット通販の家電は、実店舗よりなぜ安いのかという魅力がある一方で、購入前の実物確認ができないために、思わぬ失敗談につながるケースも少なくありません。
特に、冷蔵庫のネット購入におけるデメリットやエアコン設置の注意点など、大型家電には特有のリスクが伴います。
また、万が一の初期不良が発生した際、ネットで家電を買う場合の保証はどうなっているのか、不安は尽きないでしょう。
結局のところ、家電はネットで買うか店舗で買うか、どちらが賢い選択なのでしょうか。
この記事では、ネットで買わないものとネットで買った方がいいものを明確に区別し、家電量販店で買うべきものを具体的に解説します。
さらに、家電を購入するならどこがおすすめか、家電が安くなるのは何月かといったお得な情報から、家電をネットで購入する人は何パーセントかという市場の動向まで、あなたの疑問に全てお答えします。
ネットで買わない方がいい家電の共通点と理由
ネット通販の家電はなぜ安いのか?

ネット通販で販売されている家電が、家電量販店などの実店舗よりも安い価格で提供されているのには、明確な理由があります。
最大の要因は、店舗運営にかかるコストの違いです。
実店舗を運営する場合、店舗の賃料や土地代、膨大な数の商品を展示・管理するための光熱費、そして接客を行う多くのスタッフの人件費など、さまざまな固定費が発生します。
これらのコストは、当然ながら商品の販売価格に上乗せされることになります。
一方、ネット通販専門のショップは、物理的な店舗を持つ必要がありません。
これにより、賃料や人件費といった主要なコストを大幅に削減できるのです。
削減できたコスト分を商品の価格に還元できるため、実店舗よりも安い価格設定が可能になります。
ネット販売が安い理由のまとめ
- 人件費の削減:少人数のスタッフで全国の顧客に対応できるため、人件費を抑えられます。
- 店舗コストの削減:実店舗にかかる家賃や光熱費が不要です。
- 在庫管理の効率化:倉庫を一元化することで、在庫管理コストを最適化できます。
- 大量仕入れ:全国を商圏とすることで大量に仕入れ、仕入れ単価を下げることが可能です。
また、ネット通販では、モデルチェンジによって型落ちとなった製品や、外箱に傷がついた「訳あり品」などがアウトレット品として販売されやすい傾向もあります。
これらの要因が組み合わさることで、消費者は魅力的な価格で家電を手に入れることができるのです。
実物確認ができないことの危険性

ネット通販の価格的なメリットは大きい一方で、購入前に商品を直接見て触れる「実物確認」ができないという、見過ごせないデメリットが存在します。
スペック表の数値や商品説明、レビューだけでは決して分からない、感覚的な要素でのミスマッチが購入後の後悔につながる危険性があるのです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
サイズ感や存在感
冷蔵庫や洗濯機などの大型家電は、寸法を測って設置場所に収まることを確認しても、実際に置いてみると「思ったより圧迫感がある」「色が部屋の雰囲気に合わない」と感じることがあります。
商品の「寸法」と、空間に置かれた際の「存在感」は必ずしも一致しません。
操作感や使い勝手
電子レンジのボタンの押しやすさ、掃除機の持ち手の握り心地、炊飯器の蓋の開閉のスムーズさなど、日常的に使う家電の操作感は非常に重要です。
これらの感覚は、実際に触れてみなければ分かりません。
動作音の大きさ
「静音設計」と記載があっても、音の感じ方には個人差があります。
特に、寝室やワンルームのような静かな環境で使う冷蔵庫や空気清浄機、エアコンなどの動作音は、実際に聞いてみないと許容範囲かどうかの判断が難しいでしょう。
注意:スペックだけでは分からない!質感・色味・素材感・重量感は写真では伝わりにくく、高額や長期使用の家電ほど実物確認できないリスクが大きいです。
【参考動画】家電レビュワーによる使用感比較
掃除機の吸引音やドライヤーの風量など、文章では伝わりにくい「使用感」を動画で確認するのも一つの手です。
多くの家電レビュワーが実際の使用感を比較した動画を公開しています。
このように、スペック表だけを頼りに購入を決めてしまうと、「こんなはずじゃなかった」という事態に陥りかねません。
これが、実物確認ができないことの最も大きな危険性と言えるでしょう。
ネット購入でよくある失敗談とは?

手軽で便利なネットでの家電購入ですが、その手軽さゆえに確認を怠ってしまい、後悔につながる失敗談も後を絶ちません。
ここでは、特によく聞かれる代表的な失敗例をいくつかご紹介します。
失敗談1:大型家電が搬入できない
これは最も深刻かつ頻繁に起こるトラブルです。
冷蔵庫やドラム式洗濯機を購入したものの、いざ配送日になったら「玄関を通らない」「階段を曲がれない」といった理由で搬入を断られてしまうケースです。
設置場所の寸法は測っていても、そこまでの経路である廊下の幅やドアの高さ、エレベーターのサイズなどを見落としてしまうことが原因です。
最悪の場合、キャンセル料や往復の送料を請求されたり、クレーンでの吊り上げ搬入で数万円の追加費用が発生したりすることもあります。
【リアルな声】X(旧Twitter)での失敗談
SNSで「冷蔵庫 搬入できない」と検索すると、多くのリアルな失敗談が見つかります。
こうした実体験は、何よりの教訓になります。
冷蔵庫が搬入できないがために分解されるポストくん pic.twitter.com/Qdn98F3AlF
— あんちょび (@andukusk567) December 13, 2022
失敗談2:設置環境に合わず使えない
購入した家電が、自宅の設備に対応していないケースです。
- 洗濯機:防水パンのサイズが合わない、蛇口の位置が低くて取り付けられない。
- エアコン:設置したい場所に専用コンセントがない、壁の材質が特殊で取り付けられない。
- 食洗機:分岐水栓の取り付けが自分でできず、別途業者に依頼する必要があった。
これらの場合も、設置のために追加の工事や部品が必要になり、結局は高くついてしまったという結果になりがちです。
失敗談3:思っていた機能や性能と違った
「実物確認ができないことの危険性」とも関連しますが、スペックの解釈を間違えてしまう失敗例です。
「音が静かだと思ったのにうるさかった」「吸引力が強いというレビューだったが物足りない」「海外メーカー品で説明書が分かりにくく、機能を使いこなせない」など、期待値と実際の性能とのギャップが不満につながります。
これらは、ネットの情報だけを鵜呑みにせず、一度実店舗で確認していれば防げた可能性が高い失敗と言えるでしょう。
ネット購入での初期不良のリスク

どんなに信頼できるメーカーの製品であっても、一定の確率で発生するのが「初期不良」です。
家電が届いていざ使おうとしたら「電源が入らない」「正常に動作しない」といった問題に見舞われる可能性があります。
実店舗で購入した場合、多くは店舗に持ち込むか連絡すれば、交換や修理の手続きをスムーズに進めてもらえます。
しかし、ネット購入の場合、この初期不良時の対応が煩雑になるリスクがあります。
ネット購入時の初期不良対応の流れ
ネットショップによっては、初期不良の対応について「お客様ご自身で直接メーカーのサポートセンターへご連絡ください」と定めている場合があります。
この場合、以下のような手間が発生します。
- 自分でメーカーに連絡し、症状を説明する。
- メーカーの指示に従い、製品を送り返す(梱包も自分で行う)。
- 修理または交換品が届くのを待つ。
このプロセスは、販売店が間に入ってくれる場合に比べて時間も手間もかかることが少なくありません。
特に大型家電の場合、再梱包や発送作業は非常に大きな負担となります。
また、販売店、メーカー、配送業者の間で情報連携がスムーズにいかず、対応が遅々として進まないというケースも考えられます。
購入しようとしているネットショップのWebサイトで、「返品・交換について」や「保証規定」のページを事前に熟読し、初期不良が発生した場合の連絡先や手続きの流れを正確に把握しておくことが、万が一のリスクに備える上で非常に重要です。
ネットで家電を買う保証の確認点
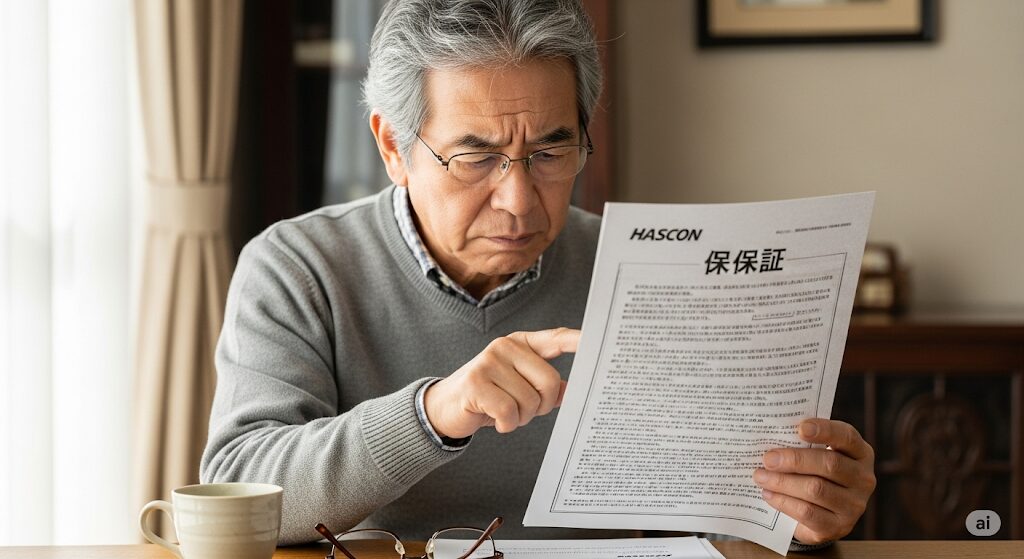
家電を安心して長く使うためには、購入後の保証が欠かせません。
家電の保証には、主に製造元であるメーカーが提供する「メーカー保証」と、販売店が独自に提供する「延長保証」の2種類があります。
ネットで家電を購入する際は、これらの保証内容がどうなっているのかを、注文を確定する前に必ず確認する必要があります。
特に注意すべきポイントは以下の通りです。
延長保証の有無と内容
メーカー保証は通常1年間ですが、故障は2年目以降に発生することも多々あります。
そのため、家電量販店では5年や10年といった長期の延長保証サービスを用意しています。
ネットショップでも同様のサービスがありますが、その内容は千差万別です。
- 保証は無料か有料か:大手家電量販店の公式サイトでは無料の長期保証が付くことが多いですが、モール型のECサイトなどでは有料オプションとなっている場合があります。
- 保証の対象範囲:自然故障(製品内部の不具合)のみが対象か、落下や水濡れなどの物損事故もカバーされるかを確認しましょう。
- 保証期間中の修理回数や上限金額:修理回数に制限があったり、修理金額の上限が購入金額までと定められていたりするケースもあります。
保証申請の手順と連絡先
故障した際に、どこに連絡すればよいのかを明確にしておくことも重要です。
前述の通り、販売店が窓口となってくれるのか、それとも自分でメーカーや保証会社に連絡する必要があるのかでは、手間が大きく異なります。
出張修理に対応しているか、修理期間中に代替機を貸し出してくれるか、といったサポート体制も確認しておくと、より安心です。
チェックリスト:保証で確認すべきこと
- 延長保証は付いているか(無料か有料か)
- 保証期間は何年間か
- 自然故障以外の物損事故も対象か
- 修理回数や金額に上限はないか
- 故障時の連絡先はどこか(販売店かメーカーか)
- 出張修理に対応しているか
価格の安さだけに目を奪われず、保証という「安心」も含めたトータルコストで判断する視点が、賢い家電選びには不可欠です。
具体的にネットで買わない方がいい家電とは?
具体的にネットで買わないもの一覧

結論から言うと、「絶対にネットで買ってはいけない」という家電はありません。
しかし、購入後のトラブルや後悔のリスクを考えると、特に慎重になるべき家電カテゴリが存在します。
それらは主に以下の2つの特徴に分類できます。
| カテゴリ | 具体的な家電製品 | ネット購入を避けるべき理由 |
|---|---|---|
| 設置や搬入が複雑な大型家電 | 冷蔵庫、洗濯機(特にドラム式)、大型テレビ(65インチ以上など)、マッサージチェア | 搬入経路の確認ミスや、設置環境との不適合が起こりやすい。トラブル発生時の追加費用が高額になるリスクがある。 |
| 使用感や感覚的な要素が重要な家電 | 掃除機、ドライヤー、シェーバー、美容家電、キーボード、スピーカー | 重量感、操作音、風量、剃り心地、打鍵感、音質など、スペックだけでは判断できない要素が多く、ミスマッチが起こりやすい。 |
これらの家電は、ネットの情報だけで購入を判断するのが難しいものです。
もちろん、購入したい製品の型番が明確に決まっていて、設置や搬入の条件もすべてクリアしていると確信が持てる上級者の方であれば、ネット購入も選択肢に入ります。
しかし、少しでも不安がある場合や、初めて購入するジャンルの製品である場合は、一度実店舗に足を運び、専門のスタッフに相談したり、実機に触れたりしてから判断することを強くおすすめします。
冷蔵庫ネット購入のデメリット解説

数ある大型家電の中でも、冷蔵庫は特にネット購入でのトラブルが起きやすい製品の一つです。
その理由は、「搬入」と「設置」という2つの大きなハードルが存在するからです。
デメリット1:搬入経路の確認がシビア
冷蔵庫の搬入で確認すべきなのは、本体の幅・奥行き・高さだけではありません。
梱包された状態でのサイズを考慮し、自宅の玄関ドア、廊下、階段、キッチンの入り口など、すべての経路を問題なく通過できるかを確認する必要があります。
特に見落としがちなのが以下のポイントです。
- ドアノブや手すりなどの突起物
- 曲がり角での回転スペース
- マンションの共用エレベーターのサイズ
【印刷OK】冷蔵庫 搬入経路かんたんチェックリスト
購入前に、メジャーを持ってご自宅の以下の箇所を測定しましょう。
| □ 玄関ドアの幅・高さ | ( )cm × ( )cm |
| □ 廊下の最も狭い部分の幅 | ( )cm |
| □ 階段の幅・高さ・踊り場のスペース | ( )cm |
| □ エレベーターのドアの幅・高さ・奥行き | ( )cm × ( )cm × ( )cm |
| □ キッチン入り口の幅・高さ | ( )cm × ( )cm |
※測定した寸法と、購入したい冷蔵庫の「梱包サイズ」を比較してください。
デメリット2:設置スペースと放熱スペースの確保
冷蔵庫は、本体が収まるだけでなく、熱を逃がすための放熱スペースが周囲に必要です。
壁にぴったりつけて設置すると、冷却効率が落ちて電気代が高くなったり、故障の原因になったりします。
必要なスペースは機種によって異なるため、ネットで購入する場合は自分でメーカーサイトなどを調べて確認しなければなりません。
【便利リンク】メーカー公式サイトの購入前チェックシート
大手メーカーは、搬入や設置に関する詳細なチェックシートを公式サイトで公開しています。
購入前に一度確認しておくことを強くおすすめします。
古い冷蔵庫のリサイクル処分も忘れずに!古い冷蔵庫の処分には家電リサイクル法に基づくリサイクル料と収集運搬料が必要。ネットショップは運搬料が割高だったり引き取り非対応の場合もあるので注意。
購入と同時にスムーズに処分を依頼できる点は、実店舗の大きなメリットです。
設置工事が伴うエアコンの注意点

エアコンは、ネット通販で「本体価格が安い」という理由だけで安易に飛びついてしまうと、最終的に支払う総額が実店舗より高くなってしまうという逆転現象が起こりやすい代表的な家電です。
その理由は、エアコンが本体と設置工事をセットで考えなければならない製品だからです。
ネットで表示されている価格には、多くの場合「標準工事費」しか含まれていません。
しかし、自宅の設置環境によっては、さまざまな追加工事が必要になるケースがほとんどです。
主な追加工事の例
- 配管の延長:室内機と室外機の距離が遠い場合に必要。
- 室外機の特殊設置:屋根の上や壁面など、地面やベランダ以外に置く場合。
- コンセントの交換・電圧切替:エアコン専用のコンセントがない、または電圧が異なる場合。
- 壁の穴あけ:配管を通すための穴がない、またはコンクリート壁など特殊な材質の場合。
- 隠蔽配管への接続:すでに壁の中に配管が埋め込まれている場合。
ネット購入の場合、これらの追加工事費は、工事当日に作業員から見積もりを提示されて初めて判明することが多く、「聞いていた金額と全然違う」というトラブルに発展しがちです。
また、工事を外部の業者に委託しているネットショップも多く、工事の品質やトラブル時の対応に不安が残るケースもあります。
【口コミ情報】追加工事費用の実態
価格.comやYahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでは、「エアコンの追加工事でいくらかかりましたか?」といった具体的な質問と回答が多数投稿されています。
こうしたリアルな情報を参考に、予算を多めに見積もっておくことが重要です。
エアコンの工事費について質問です。 パテ代というのを工事費以外に 別途1,100円(税別)請求されました。 先にエアコンを購入した家電量販店で 工事費を15,000円支払っているのですが、 こういったものは工事費に含まれていると思っていましたが違うのでしょうか?
家電量販店で 工事費を15,000円支払ったのなら、それは標準工事費用だと思います。家電量販店の内部規定で仕様は決まっていると思います。 現場で追加請求されたのは、標準工事では無かったからでは無いでしょうか?
安心を重視するなら、購入前に現地見積もりを行ってくれ、工事保証もしっかりしている実店舗での購入が断然おすすめです。
家電量販店で買うべきものリスト

これまで解説してきたリスクを踏まえると、やはり家電量販店などの実店舗で購入した方が安心な製品というものが存在します。
ネットの利便性も享受しつつ、賢く使い分けるために「店舗で買うべきもの」を整理しておきましょう。
1. 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの大型家電
最大の理由は、搬入・設置に関する相談や下見を専門スタッフと直接行えることです。
トラブルを未然に防げる安心感は、価格以上の価値があります。また、古い家電のリサイクル処分も同時にスムーズに依頼できます。
2. テレビ・オーディオ機器などの高額AV機器
テレビの色味やスピーカーの音質は、個人の好みが大きく影響します。
高額であればあるほど、実際に自分の目や耳で確かめてから購入したいものです。
専門知識が豊富なスタッフに、接続方法や周辺機器との組み合わせについて相談できるのも大きなメリットです。
3. 美容家電・マッサージチェアなど身体に触れる製品
ドライヤーの風量や重さ、シェーバーの肌あたり、マッサージチェアの揉み心地など、使い心地が満足度に直結する製品は、実機を試せる店舗での購入が最適です。
自分に合った製品を見つけやすくなります。
4. 新生活などで家電をまとめて購入する場合
複数の家電を一度に購入する際は、店舗であれば価格交渉の余地が生まれます。
「まとめ買い」を理由に値引きやポイント増量、配送料無料などのサービスを期待できるのは、対面販売ならではの利点です。
要するに、「専門的な知識が必要」「購入前の体験が重要」「価格交渉の可能性がある」といった要素を持つ家電は、実店舗での購入に向いていると言えます。
逆にネットで買った方がいいもの

一方で、ネット通販のメリットである「価格の安さ」と「品揃えの豊富さ」を最大限に活かせる家電もたくさんあります。
以下のような特徴を持つ製品は、積極的にネット購入を検討して良いでしょう。
1. 設置工事や搬入の心配がない小型家電
炊飯器、電子レンジ、トースター、電気ケトル、コーヒーメーカー、ドライヤーといった、コンセントに差せばすぐに使える小型の調理家電や理美容家電は、ネット購入に非常に向いています。
購入後のトラブルが起きにくく、価格メリットを純粋に享受できます。
豆知識:型番が決まっているならネット購入がお得!価格比較サイトで最安ショップを探し、店舗で下見してネットで買う“ハイブリッド型”も賢い方法です。
2. スペックが明確で比較しやすい情報家電
パソコン、モニター、プリンター、キーボード、外付けHDD、Wi-Fiルーターなどの情報家電は、性能がCPUの型番やメモリ容量、解像度といった数値で明確に示されているため、実物を見なくても性能の比較がしやすいのが特徴です。
購入者のレビューも詳細なものが多く、自分の用途に合った製品を選びやすいでしょう。
3. 交換用の消耗品やアクセサリ
空気清浄機のフィルターや、プリンターのインク、掃除機の紙パックといった消耗品は、型番さえ間違えなければどの店で買っても同じものです。
店舗よりも安く、かつ自宅まで届けてくれるネット通販での購入が最も効率的です。
このように、自分で簡単に設置・使用でき、製品の仕様が標準化されているものは、ネット購入の恩恵を受けやすいカテゴリと言えます。
ネットで買わない方がいい家電を避ける購入術
家電はネットで買うか店舗で買うか?

結局のところ、家電はネットと店舗のどちらで買うべきなのか、その最終的な判断は「何を買うか」そして「誰が買うか」によって決まります。
それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、自分の状況に合わせて最適な購入方法を選択することが重要です。
以下の比較表を参考に、ご自身のケースを当てはめてみてください。
| 項目 | ネット通販 | 実店舗(家電量販店) |
|---|---|---|
| メリット | ・価格が安い傾向にある ・品揃えが豊富 ・24時間いつでも購入できる ・自宅まで届けてくれる | ・実物を見て触って試せる ・専門スタッフに相談できる ・搬入や設置の相談がしやすい ・価格交渉ができる場合がある |
| デメリット | ・実物を確認できない ・搬入や設置にリスクがある ・保証や初期不良対応に不安な場合がある ・価格交渉ができない | ・価格が高い傾向にある ・店舗の在庫に品揃えが限られる ・営業時間に制約がある ・店舗まで行く手間がかかる |
賢い使い分けのポイント
最適な購入方法は、一つではありません。例えば、以下のようなハイブリッドな使い分けが最も賢い選択と言えるでしょう。
ハイブリッド購入術
- Step1:まず家電量販店に行き、気になる商品の実物を確認する。サイズ感、操作性、デザインなどをチェックし、専門スタッフから詳しい説明を聞く。
- Step2:購入したいモデルの型番を控えておく。
- Step3:自宅に帰り、その型番を価格比較サイトなどで検索。店舗の価格とネットの最安値を比較する。
- Step4:価格差、保証内容、送料、ポイント還元などを総合的に判断し、最もメリットの大きい方で購入する。
この方法であれば、店舗の「安心感」とネットの「価格メリット」の両方を享受することが可能です。
手間はかかりますが、高価な買い物で後悔しないためには、最も確実な方法です。
家電を購入するならどこがおすすめ?

購入先を選ぶ際には、「価格」「品揃え」「信頼性・サポート」の3つの軸で検討するのがおすすめです。
それぞれのニーズに合った購入先が存在します。
信頼性とサポートを重視するなら「家電量販店の公式通販サイト」
ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキなどの大手家電量販店が運営する公式オンラインストアは、実店舗と同等の手厚い保証やサポートを受けられるのが最大の魅力です。
価格は最安値ではないかもしれませんが、設置・工事の申し込みやアフターサービスも充実しており、特に大型家電を購入する際の安心感は絶大です。
価格と品揃えを重視するなら「大手ECモール」
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの大手ECモールは、数多くのショップが出店しており、圧倒的な品揃えと価格競争が魅力です。
ポイント還元キャンペーンなどを活用すれば、実質的により安く購入できることもあります。
ただし、出店しているショップによって保証内容やサポート体制が大きく異なるため、購入前には必ずショップの評価やレビューを確認する必要があります。
とにかく最安値を追求するなら「価格比較サイト」
「価格.com」などの価格比較サイトを利用すれば、特定の型番の商品を最も安く販売しているショップを一覧で比較できます。
ネット専業の小規模なショップが最安値であることも多いですが、その分、保証がメーカー保証のみであったり、サポート体制が限定的であったりするリスクも考慮しなければなりません。
家電の知識が豊富で、ある程度のリスクを許容できる上級者向けの選択肢と言えるでしょう。
家電が安くなるのは何月が狙い目?

家電製品は、一年を通じて価格が変動します。
急ぎでなければ、価格が下がりやすい「狙い目の時期」に購入することで、同じ製品でもよりお得に手に入れることが可能です。主なセール時期は以下の通りです。
1. 決算セール(3月・9月)
多くの企業の決算期にあたる3月と、中間決算期の9月は、販売店が売上目標を達成するために大規模なセールを行います。
在庫処分も兼ねて、多くの商品が値引き対象となる一年で最も大きなチャンスの時期です。
2. ボーナス商戦(7月・12月)
夏のボーナス時期である7月と、冬のボーナス・クリスマス商戦が重なる12月も、消費者の購買意欲が高まるため、各社がセールやキャンペーンを積極的に展開します。
3. モデルチェンジの直前
家電製品は、多くが年に一度モデルチェンジを行います。
新モデルが発売される1〜2ヶ月前になると、旧モデルの在庫を売り切るために価格が大きく下がります。
最新機能にこだわりがなければ、性能的にほとんど変わらない旧モデルを安く手に入れる絶好の機会です。
| 家電カテゴリ | モデルチェンジが多い時期 | 価格が下がりやすい時期 |
|---|---|---|
| エアコン | 10月~11月頃 | モデルチェンジ直前、または需要が少ない冬場(11月~2月) |
| 冷蔵庫 | 9月~10月頃 | 8月~10月頃 |
| 洗濯機 | 7月~8月頃 | 6月~8月頃 |
| テレビ | 5月~6月頃 | 4月~6月頃 |
これらの時期を意識して購入計画を立てることで、賢く節約することができます。
家電をネットで購入する人は何パーセント?

近年、家電製品をオンラインで購入する消費者の割合は増加傾向にあります。
経済産業省が発表している「電子商取引に関する市場調査」は、この動向を把握するための信頼できる情報源の一つです。
最新の調査結果によると、2022年の「生活家電・AV機器・PC・周辺機器等」のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は2兆5,528億円にのぼります。
そして、このカテゴリにおけるEC化率(すべての商取引に占める電子商取引の割合)は42.01%に達しています。(参照:経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査」)
EC化率とは?
EC化率とは、すべての商取引の金額(市場規模)のうち、EC(ネット通販)が占める割合を示す指標です。
家電分野のEC化率が42.01%ということは、販売されている家電製品の約4割がインターネット経由で購入されていることを意味します。
この数値は、2019年の32.75%から大きく上昇しており、特にコロナ禍を経て、消費者が家電のような比較的高額な商品でもオンラインで購入することへの抵抗が少なくなったことを示唆しています。
もはや「家電をネットで買う」ことは、一部の詳しい人だけが行う特殊な行動ではなく、ごく一般的な購買スタイルの一つとして定着したと言えるでしょう。
だからこそ、ネット購入のリスクを正しく理解し、賢く利用するスキルがこれまで以上に重要になっているのです。
後悔しないネットで買わない方がいい家電の選び方
この記事の要点をまとめました。
ネットと実店舗のメリットを上手に使い分け、後悔のない家電選びをしてください。
- ネット通販の安さは人件費や店舗コストの削減が理由
- 実物確認できないサイズ感や操作音、質感は大きなリスクとなる
- 大型家電の搬入失敗はネット購入で最も多いトラブル
- エアコンは本体価格だけでなく工事費を含めた総額で判断する
- 初期不良時の対応が店舗より煩雑になる可能性を考慮する
- 購入前に販売店の保証内容と延長保証の有無を必ず確認する
- 設置や搬入が複雑な大型家電は実店舗での購入が安心
- 冷蔵庫は搬入経路と放熱スペースの確認が不可欠
- 使用感が重要な美容家電や音響機器は実店舗で試すのが基本
- 逆に設置不要な小型家電や情報家電はネット購入向き
- 購入先は信頼性の高い家電量販店の公式通販がおすすめ
- 価格を重視するなら大手ECモールや価格比較サイトを活用する
- 家電が安くなるのは決算期、ボーナス商戦、モデルチェンジ前
- 店舗で下見してネットで買うハイブリッドな方法が最も賢い
- 現在では約4割の家電がネットで購入されている
【困ったときは】消費生活相談窓口
ネット通販に関するトラブルで困った場合は、一人で悩まずに専門の窓口に相談しましょう。
消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます。